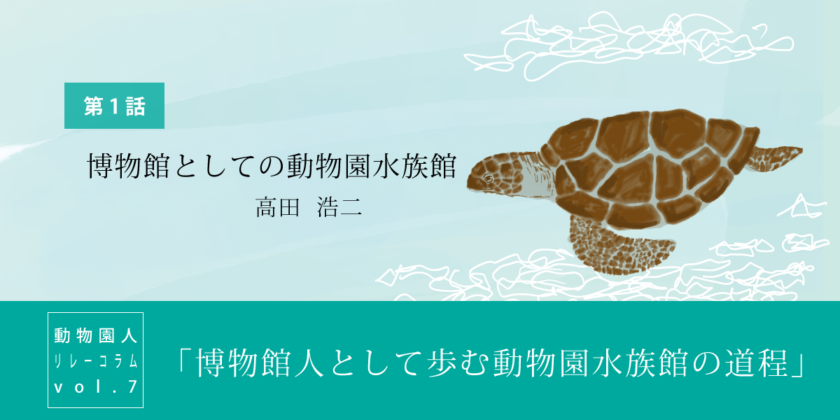
目次
1.学生が抱く“博物館”のイメージと動物園水族館のギャップ
私は長年、大学の学芸員養成課程の教鞭を執ってきた。
毎年、講義の冒頭で私のプロフィールを語ると、「なぜ水族館業界の人が博物館学を教えるのだろうか」と怪訝そうな顔をされる。
また、「動物園水族館も博物館だと思いますか」と尋ねると、半数以上からは否定的な反応が返る。
つまり大学生にとっての博物館は、歴史や考古、美術などの資料を扱う施設であり、また自然科学系では自然史や科学までがその範疇で、動物園水族館は博物館とは別物だという認識なのだ。
2.博物館法に見る、動物園水族館の本来の立ち位置
しかし我が国の、1951年に制定された博物館法の第二条の定義には、“博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関”と記されている。
つまり、博物館が集める資料には「自然科学等に関するもの」も含まれており、自ずと動物園、水族館、植物園も定義に沿った活動をする機関として存在しているのであれば、立派な博物館の仲間である。
加えて資料の保管には「育成を含む」と補記されていて、命のある生きた資料を扱う動物園水族館に限りなく配慮していると言える。
3.“レジャー施設”というラベリングがもたらした構造的な誤解
でありながら、なぜ学生たち(もっと広めれば一般の人々)は、動物園水族館と博物館を区別しているのだろうか。
まず収集活動において動物園では、フィールドからではなく昨今の事情で、大半は繁殖や交換、譲渡(稀に保護)などで補っている。
一方水族館ではそれに加えて、近隣の水域での自家採集と漁業捕獲の一部から、また観賞魚販売店からの仕入れもある。
しかしながら、他の博物館のような調査研究を伴いながらの入手は希薄で、単なる欠品補充の要素が強い。
つまり、動物園水族館の資料は「死んだら除却」される運命にあり、収蔵庫に累々と研究資料として積み重なってはいかない。
さらに認識祖語の要因は、当事者や利用者にとっても社会教育機関であることの意識欠落が最も大きい。
つまり、前述定義の中の「教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する」という機能が著しく欠如し、「レクリエーション等に資するために必要な事業」に大きく傾倒してきたものと類推できる。
4.教育・研究機能を持つ「博物館」としての責任が求められている

事実、博物館法制定時にも、動物園水族館の扱いは、戦後復興期の我が国において国民の余暇や休息のための公園、レジャー的機能のほうが注目されがちでもあった。
このことから、文部省(当時)よりも厚生省(当時)の管轄下に置くべきとの議論もあり、特に公立動物園では教育部局(教育委員会)よりも公園緑地や建設部局などに所管され、それが施設を博物館登録する足かせにもなったことは否定できない。
つまり、公営も民営も動物園水族館に求める最大の機能は余暇、レジャー、休息であり、現場はそれに従順であり続けてきたことが最も大きな原因である。
また獣医師はいても学芸員の配属は長年なされていなかったのも事実だ。
私はこのような解釈の違いを、法制度や当事者、一般市民の責任とは思っていない。
また、余暇、休息、公園、レジャー、レクレーションの機能を教育機能よりも下に見ているのでもない。
ただそれらの役割以外に、収集、調査研究、保管、展示、教育という、法律で求める博物館機能があることの自覚が内外にも必要であり、繰り返すが法律上、動物園水族館は博物館であるのだ。
その社会責任を当事者である動物園水族館が果たさずして、近年、強く求められている、動物福祉、種の保存、生物多様性の役割にも本当に寄与できるのかと思うからでもある。
5.教育産業としての進化が、リスクマネジメントにもつながる
さらに言えば、レクレーションやレジャーの観光需要は流動的であり、国際情勢等により一気に出口を止められることもある。
本稿を書いている今も、米国の政局の影響で株価は暴落し、不安定な国際関係や国内経済も先行きが不安である。
その前にも私たちは、2020年から数年間、COVID-19と命名された感染症に苦しめられた経験もしている。
一方、教育普及は我が国には「義務教育」や「生涯教育」という概念がある。
小中学校まで教育は国民の義務であり、高校大学も全入時代が到来した。その後も人の学びは一生涯続くのである。
つまり、教育の相手は巨大(マス)でありその利用先として私ども動物園水族館が選ばれることは、大きな経営戦略としてとらえていく必要があり、それはある意味リスクマネジメントでもある。
私は動物園水族館が、一つの「教育産業」として言えるくらいの成長と変革をすべきという考え方を提言し続け、長年そのための多用な教育実践にも取り組んできた。
動物園水族館は社会教育機関として教育機能で生き残りをかけてほしいと切に願い、
そして堂々と「我々は博物館だ」と名乗り、人々の意識改革も目指していただきたい。
寄稿者profile
略歴
1953昭和28年 大分県生まれ
1976昭和51年 東海大学海洋学部水産学科卒業
1976昭和51年 大分生態水族館(マリーンパレス)入社
1988昭和63年 海の中道海洋生態科学館(マリンワールド海の中道)入社
2002平成14年 福岡大学非常勤講師
2004平成16年 国立民族学博物館客員教授
2004平成16年 海の中道海洋生態科学館館長
2005平成17年 博士(学術)東海大学海洋教育における水族館の役割に関する研究
2007平成19年 文部科学省学芸員の養成に関するワーキンググループ委員
2015平成27年 福山大学生命工学部教授
2019平成31年 海と博物館研究所設立同所長
2019平成31年 文化庁博物館部会委員
2021令和3年 福岡ECO動物海洋専門学校非常勤講師
2024令和6年 船の科学館特任学芸員

著書(共編・共著含む)
- 博物館をみんなの教室にするために(高稜社書店)
- 博物館学講座10巻、13巻(雄山閣出版)
- 魚のつぶやき(東海大学出版会)
- 水族館の仕事(東海大学出版会)
- 海のふしぎ「カルタ」読本(東海大学出版会)
- 居酒屋の魚類学(東海大学出版会)
- 47都道府県・博物館百科(丸善出版)
- 動物園と水族館の教育(学文社)
- 海の学びガイドブック社会教育編(大日本図書)